 灯
灯仕事が忙しくて勉強する時間がありません…
忙しくて勉強する時間がない人こそ、先に勉強時間を確保してしまうことが重要です。
1日の中に1時間なり2時間なり勉強時間の枠を決めて、その時間に合わせて生活をやりくりするわけです。
私はこれを「先取り時間術」と呼んでいます。
働きながら勉強したいと考えている社会人にとって、勉強時間の確保は避けて通れない問題です。
勉強時間を作るために、いろいろなライフハックや時短術を試してみたものの、あまりうまくいかなかったという人もいるかもしれません。
時間術の「王道」は、余った時間を使うことではなく、まず大事なことに時間を使うことです。
今回は、忙しい独学兼業受験生でも自分のための時間が確保できる先取り時間術について考察していきます。
この記事を読めば、時短術に頼らずに、あなたの勉強時間を最大化できる時間の仕組みが手に入ります。


- 大学受験の指導経験は10年以上
- 自身も行政書士試験に独学で合格
- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中
時間はお金と同じ:なぜ「浪費・消費・投資」で分けるのか



「先取り時間術」って何ですか?
1日は24時間しかありません。
これは誰にとっても平等な事実です。
そして、時間は貯蓄できません。
将来のために取っておくことも、翌日に繰り越すこともできません。
だからこそ、勉強時間を確保するには、何かを手放すトレードオフが必要になります。
このとき参考になるのが、家計管理で使われる「浪費・消費・投資」の考え方です。
時間も同じように分類できます。
目的なく消えていく時間は「浪費」、生活維持に必要な時間は「消費」、未来の自分を育てる時間は「投資」。
勉強時間を増やすには、「浪費」を「投資」に変えていくしかありません。
| 分類 | 意味 | お金の場合 | 時間の場合 |
|---|---|---|---|
| 浪費 | 目的なく消えていく使い方 | 衝動買い・使途不明金 | なんとなくSNS・惰性の動画視聴 |
| 消費 | 生活維持に必要な使い方 | 食費・光熱費・交通費 | 睡眠・食事・仕事・家事 |
| 投資 | 未来の自分を育てる使い方 | 貯金・投資・教育費 | 勉強・読書・創作・運動 |
このように、時間というのはお金によく似ています。
まさしく「タイム・イズ・マネー」です。
先取り時間術:まず勉強時間の枠を決める



でも、時間のやりくりが大変なんです…
時間をお金のように考えると、貯金術の知恵を時間術に応用することができます。
たとえば、貯金の王道に「先取り貯金術」という方法があります。
生活費の余りを貯金に回そうとしても、なかなかうまくいかない。
しかし、給料を受け取った時点で貯金分を天引きしてしまえば、残りのお金でやりくりするようになり、着実に貯金は増えていきます。
これは「余ったら使う」ではなく、「先に取っておく」という順序の工夫です。
そしてこの考え方は、時間術にもそのまま応用できます。
「余った時間で勉強しよう」と考えていると、結局その時間は訪れません。
仕事や家事、予定外の用事に追われて、気づけば1日が終わっている。
そんな経験は誰にでもあるはずです。
だからこそ、勉強時間は「義務」として先に確保する。
1日のスケジュールの中で、まず勉強時間の枠を決めてしまう。
そのうえで、残りの時間を調整するほうが、ずっと確実なのです。


実践編:時間の棚卸しワークで無駄を見える化する



さっそくやってみます!
やりかたを教えてください。
「先取り時間術」を実践するには、まず今の時間の使い方を見える化することが大切です。
以下の手順に沿って、実際に手を動かしてみましょう。
ステップ1:1日の行動を書き出す
まずは、起床から就寝までの行動をざっくり書き出してみます。
細かくなくても構いません。
思い出せる範囲でOKです。
1日の行動を書き出す
7:00 起床
7:30 通勤
9:00 仕事開始
…
23:30 就寝
ステップ2:「浪費・消費・投資」に分類する
次に、それぞれの時間を「浪費・消費・投資」に分類してみましょう。
「浪費・消費・投資」の分類
- 浪費:目的なく消えていく時間(例:なんとなくSNS、惰性の動画視聴)
- 消費:生活維持に必要な時間(例:睡眠、食事、仕事、家事)
- 投資:未来の自分を育てる時間(例:勉強、読書、創作、運動)
この分類は絶対ではありません。
たとえば通勤は「消費」に分類されがちですが、音声教材を聴いていれば「投資」の時間と言えるかもしれません。
夜のSNS時間も「浪費」に見えるかもしれませんが、目的や気分によっては「休息」や「情報収集」として機能していることもあります。
大切なのは、自分にとってその時間がどんな意味を持っているかを見つめ直すことです。
ステップ3:固定時間の見直し
家計の見直しで「固定費」をチェックするように、時間にも「固定時間」があります。
睡眠、仕事、食事、家事など、毎日必ず発生する時間の支出です。
これら「消費」に該当する時間は、削るのではなく質や価値を高める方向で見直すのがポイントです。
家計において、固定費の節約は毎月の支出に継続的な効果をもたらします。
同じように、固定時間の質を高めることで、生活全体のリズムや満足度に長期的な恩恵が生まれます。
たとえば、睡眠の質を高める工夫をしておくと、翌朝の頭がすっきりして、勉強の効率がぐっと上がります。
食事のリズムを整えることで、だらだらとした間食が減り、時間のメリハリがつきます。
こうした小さな改善が、勉強という「投資時間」を支える力になります。
生活の再設計:勉強時間から逆算して生活リズムを作る



こうして見ると、けっこうムダな時間があったかも。
「時間の再設計」は、単なるスケジュール調整ではありません。
それは「生活の重心を勉強に移す」という構造的な再編成です。
ステップ1:浪費時間を削る
まずは、棚卸しで「浪費」と分類された時間を見直します。
SNSや動画視聴など、削れる時間を具体的に把握しましょう。
この削減可能な時間が、勉強という「投資」に回せる原資になります。
ステップ2:投資時間を増やす
次に、勉強時間として使いたい目標時間を決めます。
たとえば「1日3時間」。
もし浪費だけでは足りない場合は、「消費」時間の質を高めて余白を生み出す工夫も有効です。
食事や家事の効率を上げることで、思わぬ時間が生まれることもあります。
ステップ3:投資時間を先に置く
確保した勉強時間は、真っ先にスケジュールに置きます。
朝型・夜型など、自分の集中しやすい時間帯を活かして、生活の中に「勉強が中心にある」感覚を育てましょう。
たとえば朝は非常に勉強効率の高い時間帯です。
そこで真っ先に朝の勉強時間をセットします。
朝活については後ほど別記事で詳しく考察します。
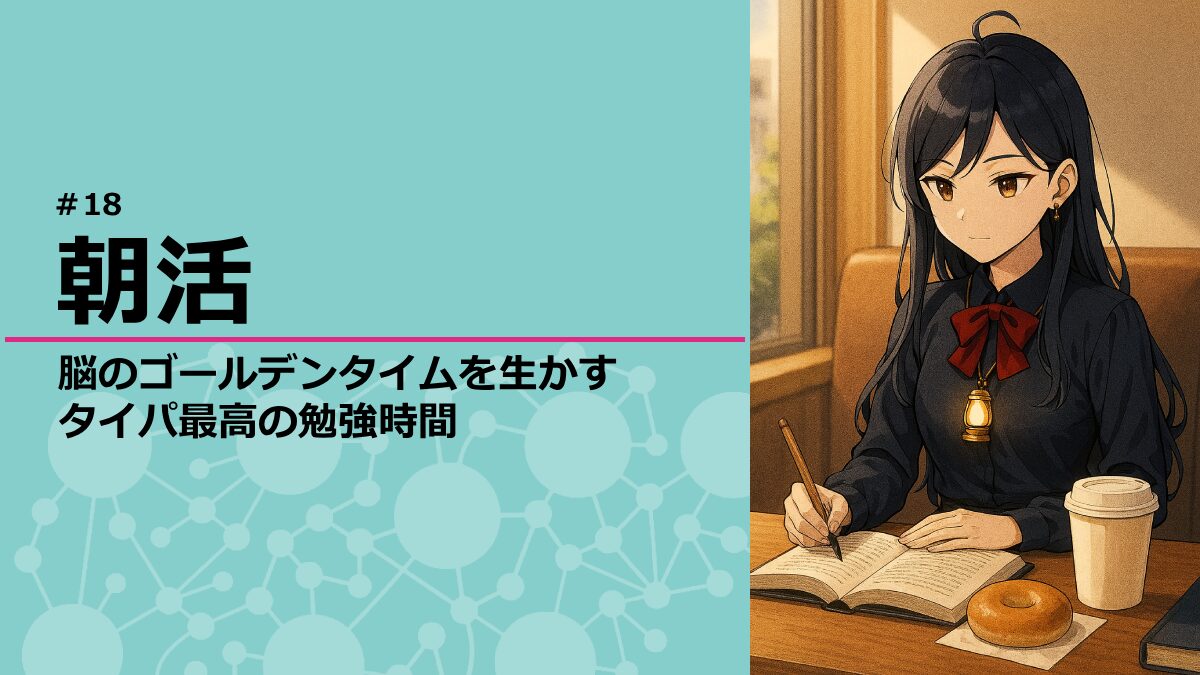
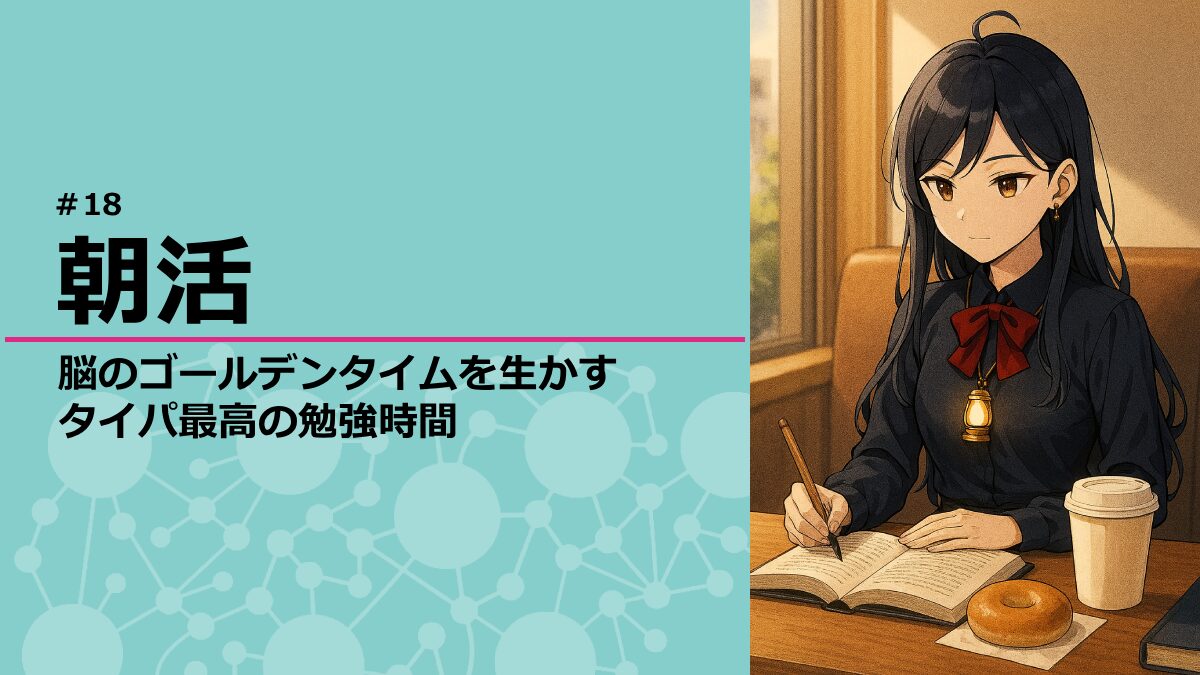
ステップ4:生活全体の再設計
最後に、生活全体を勉強中心に再設計します。
食事・休憩・移動・睡眠など、日々の活動を勉強時間のまわりに配置し直すことで、自分に合った生活リズムが少しずつ整っていきます。
時間というのはトレードオフです。
何かを増やすには、何かを減らす必要があります。
たとえば「毎日5時間勉強したい」と思っても、削れる「浪費」が2時間しかなければ、それ以上は生活の構造そのものを見直す必要があります。
絶対的な時間が足りないのに、新たな時間がどこかから降って湧いてくることはありえません。
1日24時間しかないというのは、そういう意味です。
だからこそ、「勉強時間をどこに置くか」だけでなく、生活の設計そのものを見直す視点が欠かせないのです。
勉強を中心に据えた生活リズムが整ったら、次はそれを習慣として根付かせていきましょう。
習慣化の仕組みについては別記事で詳しく考察しているので、そちらも参考にしてみてください。


効率化の罠:時短術の前に自分の時間を確保する



最初に勉強時間を確保するのが大切だったんですね!
時短術や効率的なツールは便利ですが、それだけでは時間は余りません。
世界的ベストセラー『限りある時間の使い方』では、それを「効率化の罠」と呼んでいます。
効率よく動けば動くほど、仕事は増え、忙しさは終わらない。
だからこそ、時短術は自分の時間を守ったあとに使うもの。
順番を間違えると、効率化によってさらに忙しくなるという悪循環に陥ります。
時短術は「ケチケチ節約術」と同じ。
疲弊するだけで本質的な時間の使い方は変わりません。
自分にとって大事なことに時間を使いたいなら、まずやるべきは、自分の時間をしっかりと確保することです。
Akari NOTE:先取り時間術まとめ



ここまで読んでくださってありがとうございます。
勉強時間を確保する方法について、少しずつ見えてきましたね。
最後に、この記事のポイントをまとめておきます。
自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!
- 時間もお金と同じ。「浪費・消費・投資」に分けて考えると見えてくる。
- 勉強時間は「余ったら」ではなく、「先に取っておく」のがコツ。
- まずは今の時間の使い方を見える化して、ムダを見直す。
- 勉強を中心に生活を組み直すと、リズムが整って続けやすくなる。
5分でできる行動:今日1日の行動を書き出して「浪費・消費・投資」に分類してみる



勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。



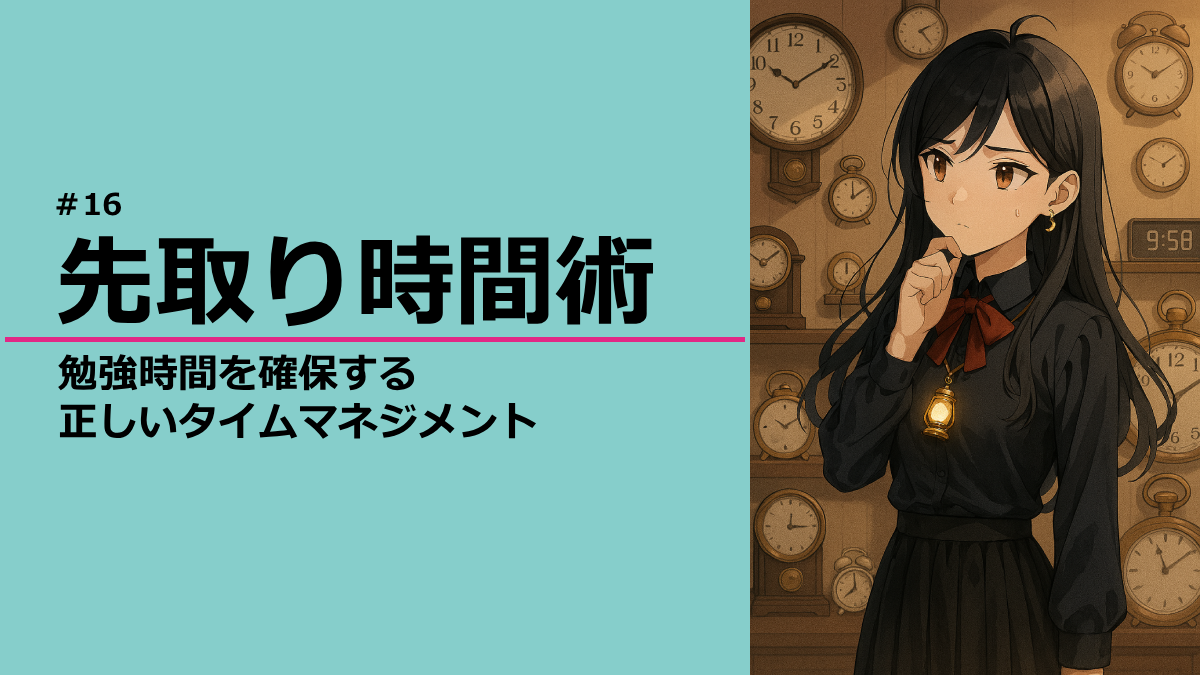

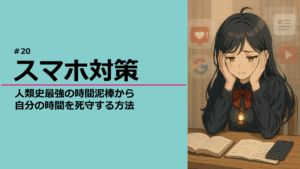
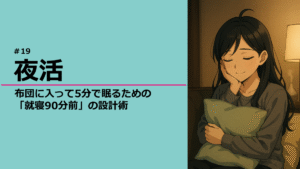

コメント