 灯
灯早起きが苦手で…。本当に朝の勉強は効率がいいの?
忙しい毎日の中で勉強時間を確保するには、先に枠をつくることが大切です。
そして、その枠をとるなら、脳のパフォーマンスが最も高い朝はおすすめです。
目覚めてから2~3時間は、脳のゴールデンタイムと呼ばれています。
この時間帯に集中することで、短時間でも質の高い学びが期待できます。
「時間がない」と感じている兼業受験生ほど、限られた時間で最大の効果を得るタイムパフォーマンス(タイパ)が鍵になります。
そこで今回のテーマは「朝活」です。
朝の静けさと脳のゴールデンタイムを味方につけることで、勉強の質と習慣が大きく変わるかもしれません。
この記事を読めば、早起きが苦手でも朝活が続く具体的な方法がわかり、タイパ最高の勉強時間を確保できます。


- 大学受験の指導経験は10年以上
- 自身も行政書士試験に独学で合格
- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中
朝の1時間が夜の4時間に匹敵する科学的根拠
冒頭でも触れたように、起床後2~3時間は脳が最高のパフォーマンスを発揮できる「ゴールデンタイム」と呼ばれています。
これは、睡眠中に脳が情報を整理し、新しい情報を処理する準備が整っているからです。
さらに、心身の疲労も回復しているため、高い集中力を発揮できます。
多くの識者が朝の勉強を推奨しているのも、この脳の状態に理由があります。
中でも『アウトプット大全』『インプット大全』などの著書で知られる精神科医・樺沢紫苑先生は、「朝の1時間には夜の1時間の4倍の価値がある」と述べています。
脳科学的に最高のパフォーマンスを発揮できる時間帯に、それに合った仕事をすることで、仕事の効率を2倍以上に高めることが可能なのです。
仕事の効率を2倍以上高めるなんて無理だろう、と思う人もいるでしょうが、私の先の「英語論文」の例を思い出してください。夜に書くのと比べて午前中に書くことで、スピードが2倍になると同時に、文章のクオリティも2倍近くアップする。効率でいうと4倍くらいの効率になったのです。
(樺沢紫苑『神・時間術』)
ウォーズマン理論のように「朝2時間=夜8時間」と単純計算はできませんが、朝のゴールデンタイムの勉強が他の時間帯より圧倒的に効率的なのは間違いありません。
この時間の価値を最大限に活かすことが、兼業受験生の成功の鍵となります。
朝活で何を勉強する? 記憶と集中力を最大化する実践ステップ



朝活ではどんな勉強をしたらいいですか?
朝のゴールデンタイムは、スーパーマリオでいうところの「スター状態」。
何を勉強してもだいたいうまくいく、そんな無敵モードです。
とはいえ、頭が冴えて集中力も高い状態だからこそ、問題集を解くなど負荷の高いアウトプットに挑戦するのがベストでしょう。
その中でも特におすすめなのが、前日に解いた問題の復習からスタートすることです。
睡眠中に整理・保存された記憶を、朝に思い出すことで、記憶の定着率がぐっと高まります。
しかも、前日に勉強したばかりの内容なので、取りかかる心理的ハードルも低く、するっと「やる気スイッチ」が入ります。
ウォーミングアップとして復習をこなしたら、調子が出てきたタイミングで、より集中力が求められる内容へ移行すると効率的。
朝のスター状態を、最大限に活かす流れです。


早起きが苦手でも続く! 通勤通学を利用した朝活



でも私、本当に早起きが苦手なんです…
自宅での朝活だと布団の誘惑に負けてしまい、なかなか習慣化できないという人は、通勤通学を利用して朝活をするという方法もあります。
2時間早く起きて、通勤ラッシュがはじまる前の電車に乗り、座席に座って楽々と読書をし、会社近くのカフェで、自分の時間を活用するという方法です。
(樺沢紫苑『神・時間術』)
実はこれ、私が高校生だった時の通学パターンにそっくりです。
私の場合、早い電車だとゆっくり座れて楽だからというのが一番の理由なんですが、電車の中では英単語集を読み、登校してから始業までの時間は図書室で数学の問題集を解いていました。
当時は朝活の効能なんて知りませんでしたけど、自然と朝のゴールデンタイムの恩恵を受けていたことになります。
経験上、それほど負担に感じることもありませんし、自然と「If-Thenプランニング」になって勉強の習慣化にも効果があるので、かなりおすすめの方法です。
朝活効果を最大化する「散歩」の活用法



朝の散歩も脳にいいって聞いたことがあります。
朝の時間に少し余裕があるなら、勉強を始める前に30分ほど散歩してみるのもおすすめです。
実はこの散歩が朝活の効果をぐっと高めてくれるのです。
まず、朝の日光を浴びることで「セロトニン」が分泌され、脳がすっきりと覚醒します。
セロトニンは、夜の睡眠を促す「メラトニン」の原料にもなるため、朝の散歩は夜の眠りにも良い影響を与えてくれます。
この2つのホルモンは自律神経のバランスにも深く関わっていて、生活リズムを整えるうえで欠かせない存在です。
さらに、軽く汗ばむ程度のウォーキングには、脳の活性化や体力の向上といった効果もあります。
集中力は体力と密接に関係しているため、散歩によって勉強の質も自然と高まります。
朝30分の散歩の効果
- 朝すっきりと目覚める
- 夜よく眠れるようになる
- 脳が活性化する
- 体力が向上する
- 集中力が向上する
このように、朝30分の散歩にはいいことしかありません。
朝の貴重なゴールデンタイムを、勉強より優先して散歩に費やす価値はあるかと問われたら、その価値は十分にあると思います。


特に夜型生活から朝型生活へ切り替えたいときには、散歩が強力な助けになります。
朝活が習慣になるまでは、まずはこの「歩く準備運動」から始めてみてください。
午後の仮眠で1日2回の朝活をする



他にも朝活のヒントはありますか?
英文学者の外山滋比古先生も、朝の勉強を強く推奨していました。
名著『思考の整理学』では、「難しい仕事は朝飯前にやると能率がよかった」と語られています。
その効果を実感してからは、意図的に朝食を抜いて「朝飯前の時間」を増やしていたそうです。
さらに印象的なのが、午後にもう一度「自分だけの朝」をつくるという発想です。
そのうちに、もう一つの手を考えた。朝食兼昼食をゆっくりとると、そこで、ひと眠りする。外で用事のあるときは、そうも行かないが、一日自由になる日は、寝る。その辺でゴロ寝、というのではない。ふとんをしいて、本格的に寝てしまう。
やがて目がさめる。いったい、いまは何時だろう。ずいぶんけさは寝坊してしまって…と、一瞬、ひるさがりを朝と取り違えるようであれば、たいへん効果的である。それをもって「自分だけの朝」とするのである。
(外山滋比古『思考の整理学』)
もちろん、社会人が午後に本格的に眠るのは難しいかもしれません。
しかし、昼食後に15~20分ほどの仮眠をとるだけでも、脳のスタミナは回復します。
朝から集中して勉強していると、午後にはどうしても脳が疲れてきます。
そこで仮眠を挟むことで、集中力をリセットし、「第二の朝」を迎えることができるのです。
この午後のリスタートは、朝活の効果をさらに高めるための生命線。
上手な仮眠の方法については、別記事でも詳しく紹介しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。


朝活を無理なく継続する逆転の発想



私もさっそく明日から朝活を始めます!
朝活を習慣化し、無理なく継続する最大の鍵は、この時間を「生活の基盤」として組み込むことです。
先ほどは電車の中で朝活するパターンを紹介しましたが、人の少ない始発電車を二度寝タイムに充て、出社前に近くのカフェなどで朝活するという逆転の発想もあります。
朝が苦手な人も、「電車に乗れば眠れる」と思えば何とか起きることができますし、駅まで歩けば軽い散歩がわりになって一石二鳥です。
いずれにせよ、朝活の力は絶大です。
ぜひ、明朝のアラームを1時間早くセットして、その効果を味わってみてください。
Akari NOTE:朝活まとめ



ここまで読んでくださってありがとうございます。
朝活について、少しずつ見えてきましたね。
最後に、この記事のポイントをまとめておきます。
自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!
- 朝は脳のゴールデンタイム。短時間でも集中力と記憶効率が最大化される。
- 朝活は前日の復習から始めると記憶が定着しやすく、心理的ハードルも低い。
- 通勤通学・散歩・仮眠などを活用することで、朝活の習慣化と効果をさらに高められる。
5分でできる行動:明日のアラームを30分早くセットして、復習ノートを机に置いておく



勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。



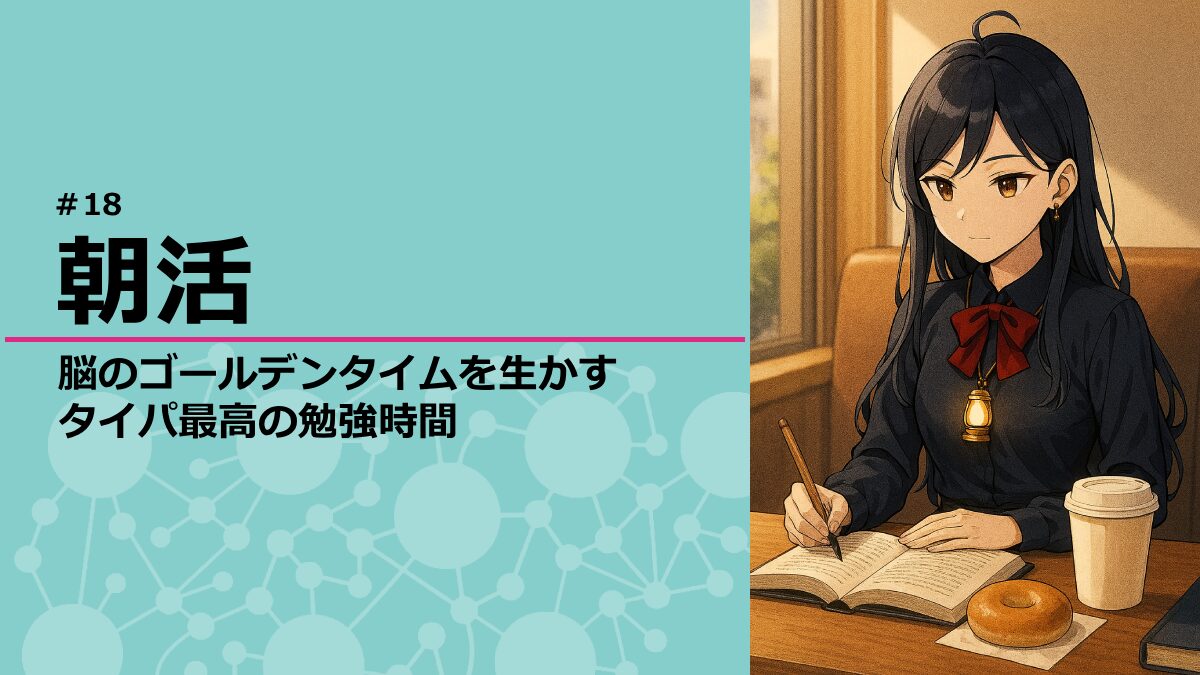

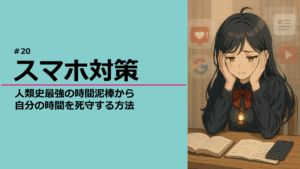
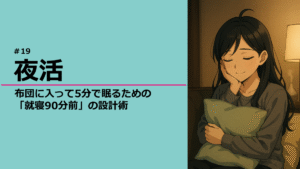


コメント