 灯
灯最近、アウトプットが大切ってよく言われますよね?
アウトプットが大切なのは、価値を生み出す可能性を秘めているからです。
インプットとアウトプットのサイクルがうまく回れば、日々の体験や学びが、すべて「知的生産」に変わっていきます。
勉強法3.0は、「知的生産のための勉強法」です。
本記事では、勉強法3.0の端緒として、ブログを軸に知的生産をしていく方法について考察していきます。
アウトプットを始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない人。
ブログを通じて、自分の思考や学びを育てていきたい人。
この記事を読むことで、軽やかに知的生産のサイクルを回す方法が見えてきます。
知的生産とは何か



そもそも知的生産って何ですか?
知的生産とは、情報を人にわかる形で発信することで、何らかの価値を生み出すことです。
知的生産の名著と名高い、梅棹忠夫『知的生産の技術』では、次のように定義されています。
かんたんにいえば、知的生産というのは、頭をはたらかせて、なにかあたらしいことがら――情報――を、ひとにわかるかたちで提出することなのだ、くらいに考えておけばよいだろう。
(梅棹忠夫『知的生産の技術』)
「価値」と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。
しかし、文章を書けば、価値というのは勝手に生まれます。
強いて言うなら、その意味のない文章に、意味づけをするのは読んだ人。
(いしかわゆき『書く習慣』)
『書く習慣』によれば、どんなにしょうもない文章でも、それを読んだ人がそれで元気になったり、共感したりすれば、その文章には価値があると言います。
文章の価値を決めるのは、書き手ではなく、読み手なのです。
この2つの視点を合わせると、考えたことをアウトプットすることそのものが、すでに知的生産であるという理屈が成り立ちます。
情報を人にわかる形で発信すれば、それを読んだ人が勝手に意味づけして、価値を見出してくれる。
つまり「情報を書いて公表すること=知的生産」なのです。
これが勉強法3.0の核になります。
なぜ知的生産の場としてのブログを選ぶのか



知的生産=アウトプットすること。
じゃあ知的生産って、どこでやればいいんですか?
今は、インターネットがあるのが当たり前の時代です。
そのおかげで、アウトプットの場はたくさんあります。
SNS、note、ポッドキャスト、YouTube動画…
でも、私が一番おすすめしたいのは、ブログです。
理由はいろいろあります。
- SNSはフロー型で情報が流れていくが、ブログはストック型で情報が蓄積されていく。
- 検索性も高く、構造化された知的資産として残る。
- 収益化や拡張性の面でも、持続可能なアウトプットの場になる。
でも、いちばんの理由は、私はブログが好きだからです。
私は以前、旅行記ブログを書いていました。
行政書士試験の勉強をする際にやめてしまったのですが、書かなくなってからの約5年間は、正直つまらなかった。
たとえば、旅行に行っても、アウトプットする意識があるから、観光というインプットの質が変わるんです。
本を読むときも、「これをどう書こうかな」と思うから、読み方が深くなる。
でも、この5年間は「アウトプットしないんだよな…」と思った瞬間、気合が入らなくなる。
思考が止まる。感情が動かない。
ブログを書かない人生って、つまんないなって思いました。
だから、本質的には、知的生産の場としては好きなところを選べばいいと思います。
でも、実体験として、ブログは知的生産の場として、思考そのものを変える力があります。
これが、私がブログをおすすめする一番の理由です。
ブログを回すための4つの要素



じゃあ、ブログってどうやって始めたらいいですか?
一言にブログといっても、いくつか選択肢があります。
しかし、本気でブログを始めるなら、WordPressをおすすめします。
立ち上げこそ少し手間がかかるものの、本当の意味で「自分のブログ」になるからです。
持ち家が資産になるように、WordPressも資産です。
この「勉研」もWordPressで作っています。
ブログ構築:WordPressの立ち上げとデザイン
今書いたように、WordPressは、無料ブログサービスに比べると、立ち上げに少し手間がかかります。
ドメインを取得して、サーバーを契約して、WordPressをインストールして、初期設定をして、ようやく記事が書けるようになります。
また、記事が書けるようになった後も、自分らしさや読者の読みやすさを考慮したカスタマイズが必要です。
そういう意味では面倒くさい。
でも、それもひとつの勉強ですし、その手間をかけるからこそブログに愛着がわくものです。
賃貸アパートはすぐに住めますが、本当に愛着がわくのは一軒家というのと同じです。
勉強法3.0では、まずWordPressの導入からブログのデザインについて考察していきます。
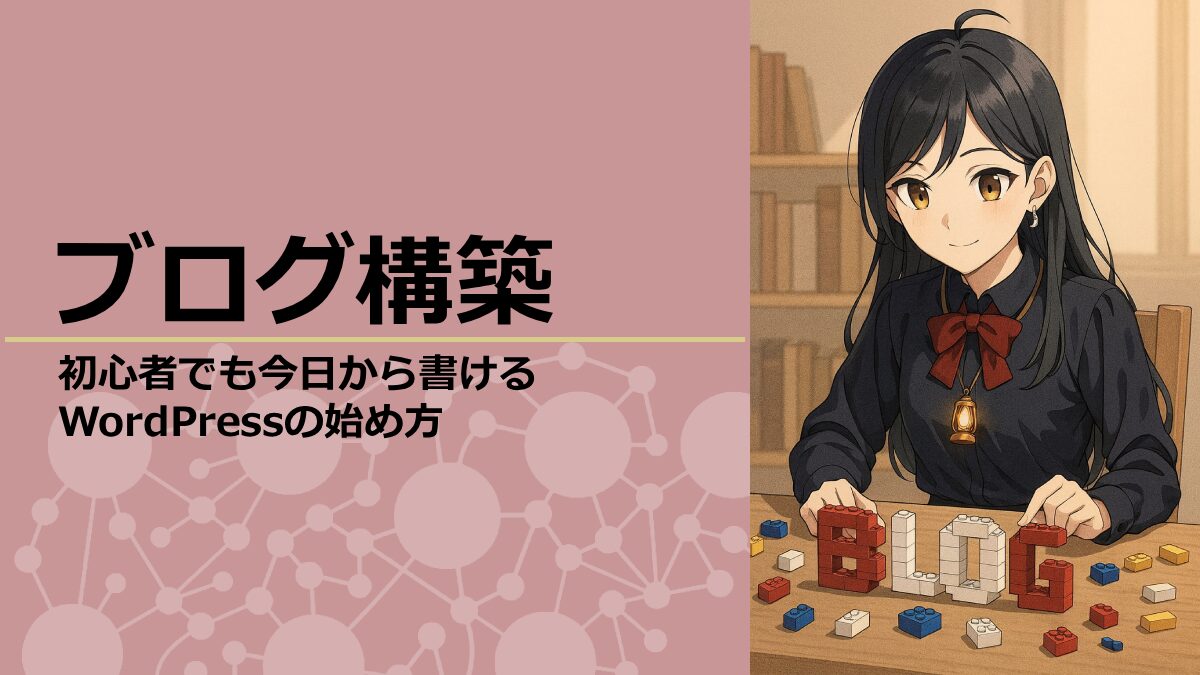
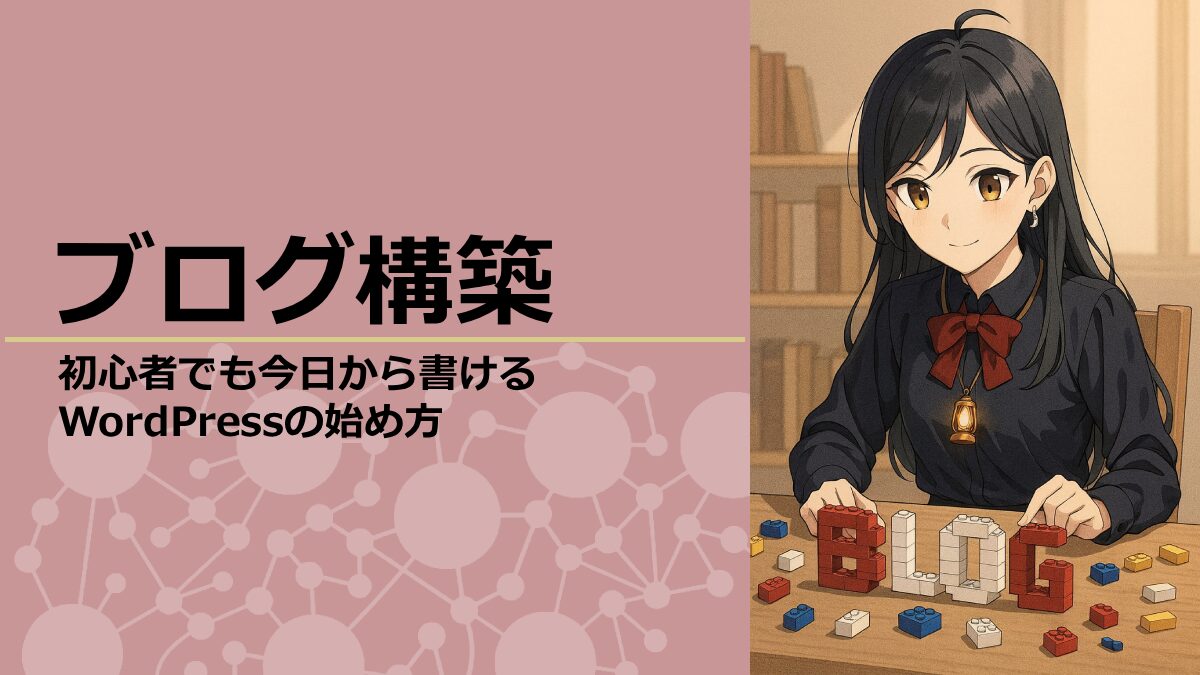
ブログ集客:多くの目に触れる
新しい体験をインプットし、そこから学んだことをアウトプットし、多くの人の目に触れることでフィードバックを得て、新たなインプットにつなげていく。
こうした知的生産のサイクルを回すには、アウトプットした文章を多くの人に読んでもらわなければなりません。
そのためには、ブログに読者を集める「集客」が必要です。
ブログの集客には、大きく分けて2つの方法があります。
ブログの集客方法
- 検索エンジンからの流入(SEO)
- SNSからの流入(XやInstagramなど)
ブログの集客には、どちらも重要です。
アウトプットした情報を、どうやって読者に届けるかというのは、勉強法3.0の大きなテーマです。
ブログ収益化:持続可能なエンジンにする
ブログの収益化も、勉強法3.0の重要なテーマのひとつです。
アウトプットによって収益が生まれれば、それは文字通り「知的生産」になります。
さらに、その収益を使って新たなインプットを得ることで、次のアウトプットにつながり、また収益が生まれ…
こうしたサイクルが回り始めると、ブログは持続可能な知的生産の場になります。
広告、アフィリエイト、note連携など、自分らしい収益モデルを設計することで、継続のための仕組みづくりを考察していきます。
収益化は、単なるお金の話ではなく、学びを続けるためのエネルギー設計でもあるのです。
ブログ文章術:伝わる文章をスムーズに書く
知的生産は、読者を前提としたアウトプットです。
そのためには、文章が伝わらなければ意味がありません。
読者が迷わず読み進められるように、文章の構成や見出しの設計を工夫することで、文章の伝達力は大きく変わります。
また、ブログを継続するためには、安定してアウトプットを続けるための技術も必要です。
ブログのための文章術は、読者との接点をつくるだけでなく、自分自身の思考を整理する手段でもあります。
よりわかりやすく、より速く、より価値のある文章を仕上げていく。
ブログを知的生産の場として育てるために、そうした文章術を、これから考察していきます。


まとめ:自分だけの知的生産エンジンを構築する
今回は、ブログを軸に自分だけの知的生産エンジンを組み立てる方法について考察してきました。
知的生産をそれほど難しく考える必要はありません。
自分のアウトプットの場をつくり、読者に発信していけば、価値は自然と生まれます。
まずは書いてみること。続けてみること。
その積み重ねが、やがて自分だけの思考の場を育ててくれます。
よりよい知的生産エンジンを、一緒に構築していきましょう。

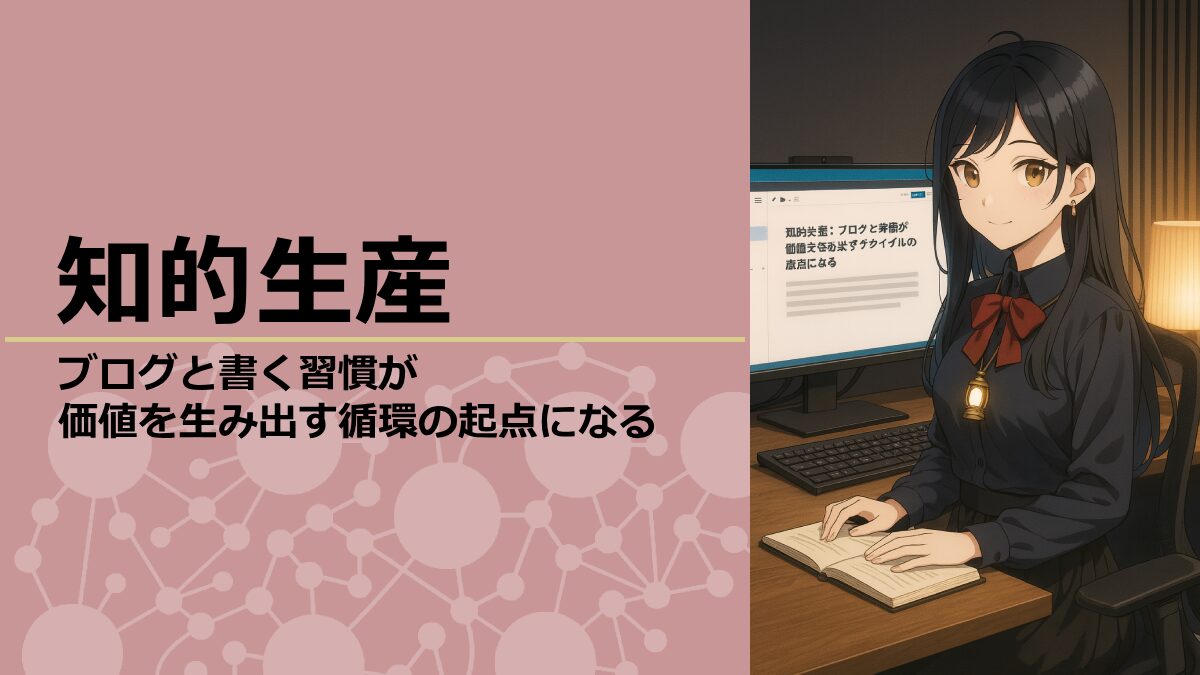

コメント