 灯
灯読書の秋ですね。
何か面白い小説はないですか?
勉強法2.0は、「人生を豊かにするための勉強法」です。
試験勉強や学校での勉強に限らず、好奇心を持って暮らしを見つめ直せば、学びは日常の中に潜んでいます。
そう聞いて最初に思いつくのは、「読書」でしょう。
そこで、勉強法2.0の最初の一歩として、私が好きな小説10タイトルを紹介します。
ちなみに「#名刺代わりの小説10選」は、その人の読書傾向や個性を表すSNSの人気タグ。
選ぶには多くの取捨選択が必要で、ちょっとした苦しみも伴います。
実は私も前からやってみたいと思っていました。
読書の秋に、もし一冊でも気になる本が見つかれば。
それはきっと、あなたの勉強法2.0の始まりになるかもしれません。
シャーロック・ホームズの冒険(アーサー・コナン・ドイル)
小学校の図書室にあったポプラ社の名探偵ホームズシリーズが、私の読書のルーツ。
その後、新潮文庫の『シャーロック・ホームズの冒険』を読んで、やはり面白いと再確認。
特に「赤毛連盟」はミステリー史に残る傑作短編でしょう。
読書感想文の宿題は、これを読んでおけば間違いなし。
文章の中からヒントを見つけ、論理を組み立てて解答を出す。
こうした国語力の基礎が鍛えられます。
ミステリーの魅力と読書の面白さを、最初に教えてくれた1冊。
世界中の全員が読むべき傑作だと思います。
三国志(吉川英治)
高校生のとき、光栄のSLGにハマったことがきっかけで、原典ともいえる吉川英治の長編小説を読みました。
前半は曹操、後半は諸葛亮無双。
通学電車で読んで夢中になるあまり、二度ほど駅で降り損ねたのはいい思い出です。
今思うと、高校時代に吉川三国志を読破したおかげで、長編や歴史小説を読む抵抗がなくなったのだと思います。
うちの妻は三国志をよく知らない人なので、手軽に三国志が学べる素材をいろいろ探した結果、吉川英治を読むのが正着という結論に達しました。
私の推しは周瑜です。
アルスラーン戦記(田中芳樹)
こちらも高校時代の思い出のシリーズです。
これと『ロードス島戦記』は、電車の中はもちろん、授業中にもよく読んでいました。
ナルサス無双。
軍師が好きなんですね。
長期休養中にカドカワでごたごたがあり、あの紫色のカバーに天野喜孝の挿絵でなくなったのが本当に惜しまれます。
執筆再開後の終盤には否定的な意見も多いですが、私を読書好きにしてくれたシリーズです。
やはり「名刺代わりの小説10選」に入ります。
火車(宮部みゆき)
私はわりかし何でも読みますが、一番好きなジャンルと問われたらミステリーです。
で、国内ミステリーで1冊というならこれ。
宮部みゆき特有の緻密すぎる描写もあり、序盤は少しかったるく感じるかもしれませんが、89ページの一言で「えっ…!?」と頭をカチ割られ、その後はノンストップです。
今にも切れそうな細い糸を、たぐり寄せて、たぐり寄せて、たぐり寄せて、ようやく真相にたどり着くのがカタルシス。
『模倣犯』と迷ったものの、1冊ですっきりまとまっている『火車』の方を。
山月記(中島敦)
ザ・格調。
「わりかし何でも読む」と言ったそばからですが、純文学は苦手です。
ただ、中島敦の文章は好きです。
高校の教科書にも載っている有名な作品ですが、その良さは大人になってから、「ああ、格調高い文章とはこういうものか」とわかりました。
うちの妻が激推ししている『悟浄嘆異』もとても良いです。
私の書く力ではこれが限界ですが。
阪急電車(有川浩)
すっと読めます。
この「すっと読める」というのは、ものすごく重要で、本当に文章がうまい人というのは、こういう文章を書くのだと思います。
そして個人的には、こういう文章を書かせたら有川浩がナンバーワンです。
憧れ。
シナリオ構成もとてもよくできていて、電車という舞台装置、少しずつ関係しあっていく登場人物、往路と復路の時間経過、そしてそれぞれの物語が恋愛というテーマで貫かれている連作短編。
絶品です。
この闇と光(服部まゆみ)
ジャンル分けの難しい異色の小説です。
読み始めた時の第一印象は、「なんだこれ?」という不思議な感覚にとらわれるものの、読み進めるにしたがって、美しく甘美な物語に引き込まれていきます。
そして、そうした美しい「闇」の世界で、主人公と読者を十分にシンクロさせたところに、あっと驚く急展開。
その後は、第1部で積み上げてきたものが、ボロボロボロボロと崩れ落ちていきます。
本作は、そうした壊れていく過程を楽しむ小説。
まだ読んでいない人が羨ましい小説として、暫定一位です。
南極点のピアピア動画(野尻抱介)
読んだのはつい最近ですけど、だからこそノスタルジーを感じるSF小説です。
正直、SF部分はどうでもよくて、いっときニコニコ動画に住んでた身としては、2010年あたりのネットの空気感を懐かしく思い出しました。
特にラストは、胸が熱くなるな。
あとは「組曲」と「ゆっくり」があれば完璧でした。
ミクさんに脳を焼かれ、弾幕を張ってキャッキャッしてた頃のネットが好きだった人にも、ぜひ読んでほしい。
どうしてこうならなかった。
あきない世傳 金と銀(高田郁)
近年では最強の徹夜本です。
『みをつくし料理帖』もそうでしたが、高田郁の物語に引き込む力はダイソン級で、仕事中以外はずっと読んで、毎晩寝落ちしていました。
本編13巻+特別編2巻という謎構成ですが、特別編まで読んで無事完結なので注意が必要です。
NHKのドラマも見ていたものの、正直あれでは原作のハラハラドキドキは伝わりません。
何なら原作の販促ドラマなのかと思ったり。
先日、新シリーズ『志記』が始まりましたが、完結するまで読まない、読めない。
高田先生、早く完結させてください。
天地明察(冲方丁)
最後は勉強法2.0らしい作品で。
江戸時代の碁打ち・渋川晴海が、日本独自の暦を作り上げるまでを描いた、史実ベースの歴史フィクション。
こう書くと難しく聞こえるかもしれませんが、実際はさくさく読める小説です。
碁打ちでありながら算術の魅力にとりつかれ、つまずきながら立ち上がる主人公・晴海。
それを清々しいまでのツンデレぶりで見守る女性・えん。
そして、晴海の素質を見抜いた天才・関孝和。
登場人物がとにかく魅力的で、そして学びに真摯で若々しい。
何かを始めるのに何歳からでも遅くない。
そう思わせてくれる一作です。
まとめ:あなたの「名刺代わりの小説10選」は?
今回は、名刺代わりの小説を10作品選んでみました。
噂には聞いていましたが、10作品に絞り込むというのは本当に苦労しました。
しかも「名刺代わり」ということで、自分の読書遍歴を象徴する作品を選ぶという縛りあり。
とはいえ、こうして完成したリストを見ると、どれも自分の人生に欠かせない作品ばかりです。
他にも紹介したい作品はまだまだありますが、それはまた別の機会に。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

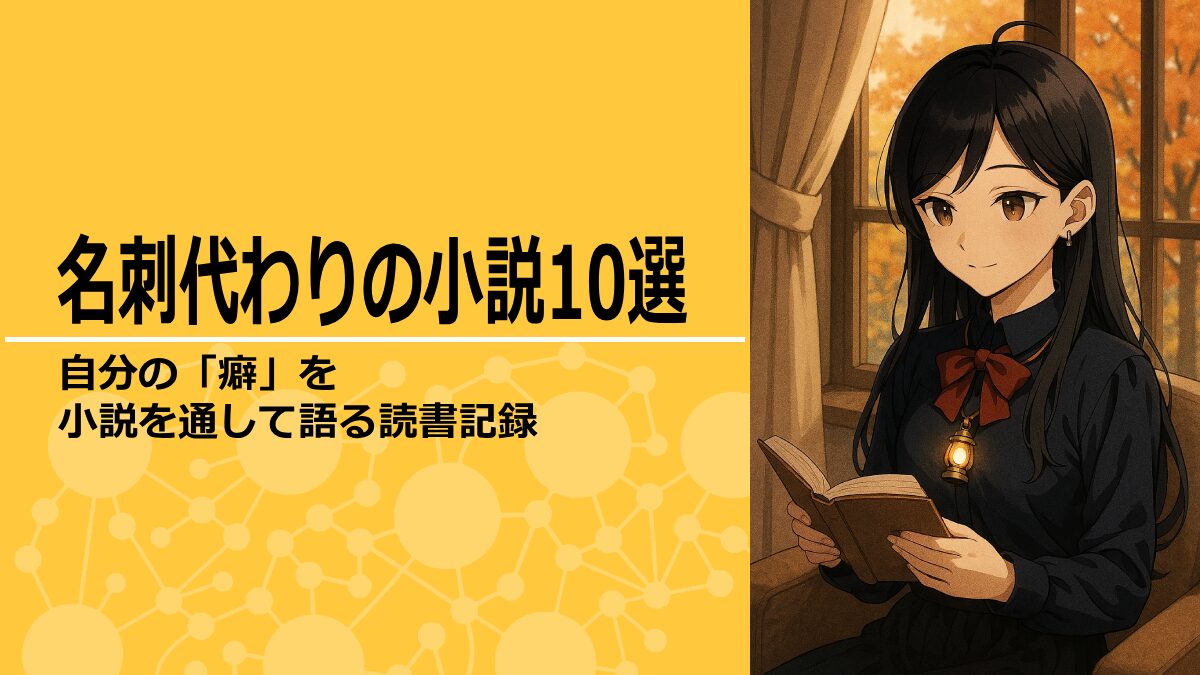




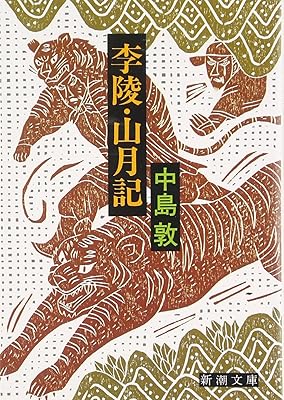

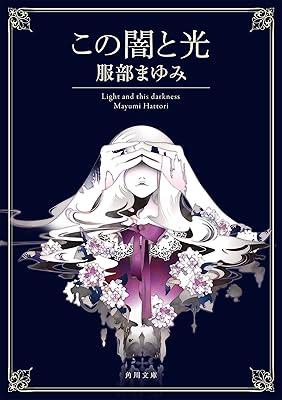


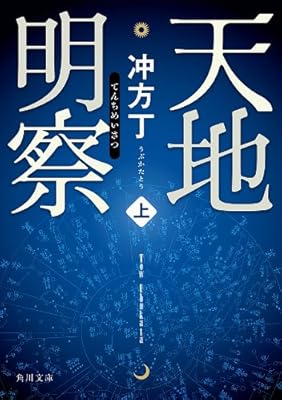


コメント