 灯
灯限られた時間で資格試験に合格するコツって何ですか?
ありふれた教科書に、当たり前に書いてある基礎的な内容を、人に教えることができるくらい徹底的に仕上げましょう。
試験勉強には、大きく分けて「入門・基礎・応用・直前」という4つのフェーズがあります。
その中でも基礎こそが本丸です。
はっきり言って、試験勉強の8割の時間は基礎の完成に費やして構いません。
むしろ限られた時間で合格するなら、その勇気を持つべきです。
特に、仕事と勉強の両立を目指す独学受験生にとって、基礎の完成は、努力と時間の無駄を防ぎ、短期合格に直結する最大の戦略です。
本記事では、試験における基礎の重要性を、試験の本質という観点から考察していきます。
この記事を読むと、基礎の本当の価値がわかり、限られた時間で効率よく合格点を超えるヒントがみつかります。


- 大学受験の指導経験は10年以上
- 自身も行政書士試験に独学で合格
- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中
まずは一般的な基礎の重要性を再確認



「基礎が大事」というのは知ってますよ?
「勉強には基礎が大事」というフレーズそのものは、誰しも耳にタコができるくらい聞いたことがあると思います。
けれども、なぜそれほど基礎が重要なのかを本当に理解している人は、意外と少ないかもしれません。
基礎というのは、単なる初歩ではなく、すべての学びの土台です。
たとえば以下のような理由から、勉強には基礎の完成が重要な意味を持ちます。
一般的な基礎の重要性
- 理解の土台になる
基礎があることで、新しい知識が「つながる」ようになります。点が線になり、線が面になる。そんな感覚が生まれます。 - 応用力の土台になる
基礎がしっかりしていると、初見の問題にも「これはあの原理が使えるかも」と判断できるようになります。応用とは、基礎の組み合わせと再構成です。 - 自信につながる
基礎が身についていると、試験本番でも「これは解ける」と思える安心感が生まれます。知識が「使える」という感覚は、心の支えになります。 - ミスが減る
計算や文法など、基礎が抜けているとケアレスミスが増えがちです。逆に、基礎が盤石なら、正確性も自然と高まります。
試験には「基礎」しか出題されない



他にもあるんですか?
とりわけ試験においては、「基礎が大事」と言われる特段の事情があります。
基礎が大事どころの話ではなく、試験の結果は基礎でしか決まらないのです。
試験の目的は「学力による選別」
そもそも試験をする目的とは何でしょうか?
もちろん合格者と不合格者を選別することは、大きな目的ではあるでしょう。
しかし、単純に合格者と不合格者を決めたいだけなら、別に抽選で決めてもいいわけです。
それをわざわざ学力考査で選別するのは、出題者が期待する学力を持った受験生だけを合格させ、そうでない受験生は不合格にしたいという基本思想があるからです。
そして、そうした学力の差をしっかり測ることのできる試験が、「フェアな試験」ということになります。
これは試験勉強を考えるうえで、非常に重要なポイントです。
マーク式試験が「基礎」に寄る理由
ところで、試験の採点にはコストがかかりますから、受験者の多い試験はマークシート式で施行されます。
記述式の出題がある試験であっても、まずはマークシート式の試験で足切りラインがあって、それをクリアした受験生の記述解答だけを採点するという形が一般的でしょう。
さて、こうしたマークシート式の試験で、受験生の全員が知らない論点を出題したらどうなるでしょうか?
マークシート式の試験は、完全に無作為でマークをしても、一定の正解者が出ることになります。
例えば5肢選択式なら、何もわからず丁半博打でマークしても、およそ20%は正解者が出ます。
これは「フェアな試験」と言えるでしょうか?
言うまでもなく、受験生の学力が結果にまったく反映されない、無意味な出題と言わざるを得ません。
つまり、受験者の全員が知らない論点を出題すればするほど、試験は丁半博打と同じになり、学力を基準に合格者を選別するという目的から逸脱してしまうことになってしまうわけです。
「基礎」こそが合格の条件
これが試験には「基礎」しか出題されない理由です。
学力考査がフェアであるためには、合格水準にある受験生なら当然知っているであろう論点だけが出題され、その正否で競い合う形でなければなりません。
つまり受験生の視点から言えば、合格水準にある受験生なら当然知っているであろう論点だけを完璧に押さえれば、必ず合格できるのです。
そして、この「合格水準にある受験生なら当然知っているであろう論点」こそ、試験における「基礎」なのです。
試験問題は「基礎・応用・逸脱」の三層構造でできている



でも、試験って基礎だけじゃ解けない問題もあるし、見たことない論点も出るじゃないですか?
それは、賢明な受験生の反応です。
実際、試験問題の中には、見慣れない形式や初見の問いが含まれていることもあります。
しかし、それらもすべて出題者が「計算して」出題しているのです。
出題者の目的は「差をつけること」
先述したように、試験の目的とは合格者と不合格者を選別することです。
角度を変えれば、とにかく全員が合格しては困るのです。
そのためには、試験の結果に差をつけなければなりません。
もし受験生の全員が知っている論点ばかりを出題し、全員が満点を取ってしまったら、それはそれで意味のない試験になってしまいます。
だからこそ、出題者は「基礎」を下地にしながらも、変化球や釣り球を駆使して、何とか受験生に差をつけようと目論んでいます。
結果として、いわゆる難関と言われる試験では、教科書に書いてある基礎的な内容が、そのままの形で出題されることはほとんどありません。
「基礎・応用・逸脱」の整理
ここで、試験問題の構造を整理してみましょう。
試験問題の構造
- 基礎:合格水準にある受験生なら当然解けるであろう問題→必ず解くべき
- 応用:受験生なら当然知っている知識から派生する問題→解けるようにしておくべき
- 逸脱:基礎から大きく外れ、むしろ手を出してはいけない問題→見抜いてスルーすべき
このうち、受験生が解かなくてはならないのは「基礎」と「応用」です。
「逸脱」は見抜く力を測る問い
それなら「逸脱」は何のために出題されるのでしょうか?
それは、「基礎でないことを知っているか」を測るためです。
基礎が怪しい受験生は、手を出してはいけない「逸脱」を見抜くことができません。
その結果、選択問題の正誤判定がブレたり、解いてはいけない設問に試験時間を費やしてしまったりして、不利な戦いを強いられます。
つまり、「逸脱」を見抜けるかどうかも、学力の一部なのです。
これなら適正な学力考査と言えますし、それこそが出題者の狙いです。
ここまでをまとめると、以下の図解です。
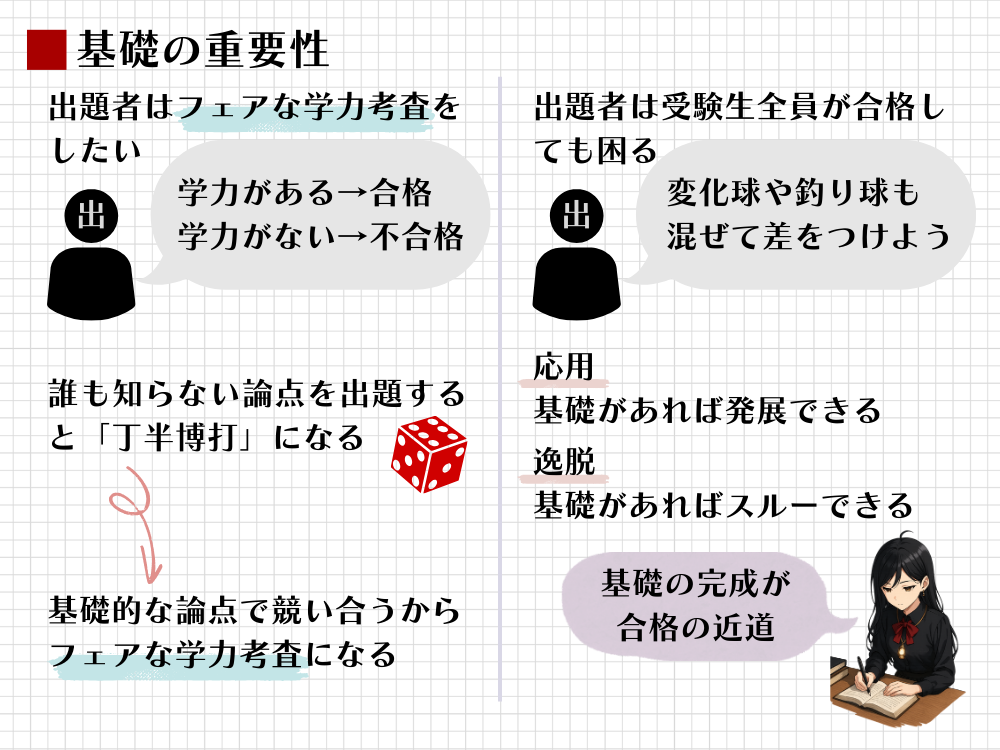
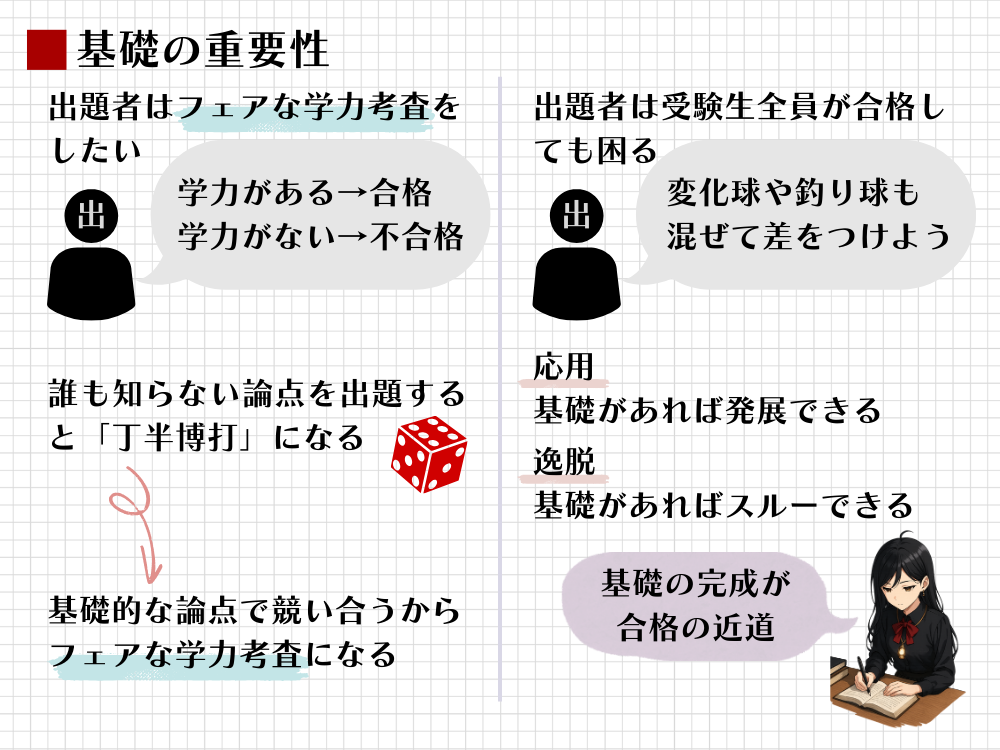
難しい問題が解けない本当の理由は「基礎の未完成」



逸脱…そんなこと考えたことなかった…
さて、ここまで読んでくださった方はお気づきでしょうか。
難しい問題、すなわち「応用」も「逸脱」も、すべて「基礎」が基準になっているのです。
基礎となる知識や理解を前提として、それを応用して得点に結びつけたり、基礎からの逸脱を見抜く力が求められる。
つまり、難問に対応する力もまた、基礎の完成度に依存しているのです。
「応用が解けない」は「基礎が未完成」のサイン
「基礎は解けるけど、応用になると解けない」という悩みはよく耳にします。
しかし、その答えはもう明らかでしょう。
難しい問題が解けない一番の理由は、「基礎が未完成だから」です。
基礎がなんとなく解けるだけで、完全には仕上がっていない。
だから応用できないというのが正確です。
応用問題は、才能やセンスの問題ではありません。
基礎がしっかりしていれば、応用は「つながって見える」ようになるものです。
「基礎=簡単」「応用=難しい」は誤解だった
多くの人が「基礎=簡単な問題」「応用=難しい問題」と考えているかもしれません。
これは、学校の教科書やワークの構成によって無意識に作られた誤解です。
多くのテキストが、単純な問題群を「基礎練習」、複雑な問題群を「応用問題」としているため、そう思ってしまうのも無理はありません。
しかし、学校で少し複雑な問題を解く本当の目的は、「基礎が十分ではないことに気づくため」です。
本当に難しいのは、「基礎を完璧に仕上げること」なのです。
試験に合格するための最短ルートは「基礎の完成」



なるほど。どうして「基礎が8割」なのか、よくわかりました。
ここまで考察してきたように、試験の結果は基礎の力で決まります。
基礎が本当の意味で完成しているなら、それを応用することは、少し練習すればできるようになるはずです。
基礎を有効に学べるテキストのセットアップを見つけることができたら、その時点で試験はほぼ勝ち確です。
あとはそのテキストに書いてある基礎的な内容を、人に教えることができるくらい徹底的に仕上げましょう。
試験勉強は基礎が8割です。
基礎を仕上げるための勉強法


Akari NOTE:基礎の重要性まとめ



ここまで読んでくださってありがとうございます。
試験勉強における基礎の重要性について、少しずつ見えてきましたね。
最後に、この記事のポイントをまとめておきます。
自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!
- 試験問題は「基礎・応用・逸脱」の三層構造でできている
- 難しい問題が解けない理由は、基礎が未完成だから
- 試験勉強は、基礎を徹底的に仕上げるのが最短ルート
5分でできる行動:頭に浮かんだ教科書の内容を生成AIに説明してみる



勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。



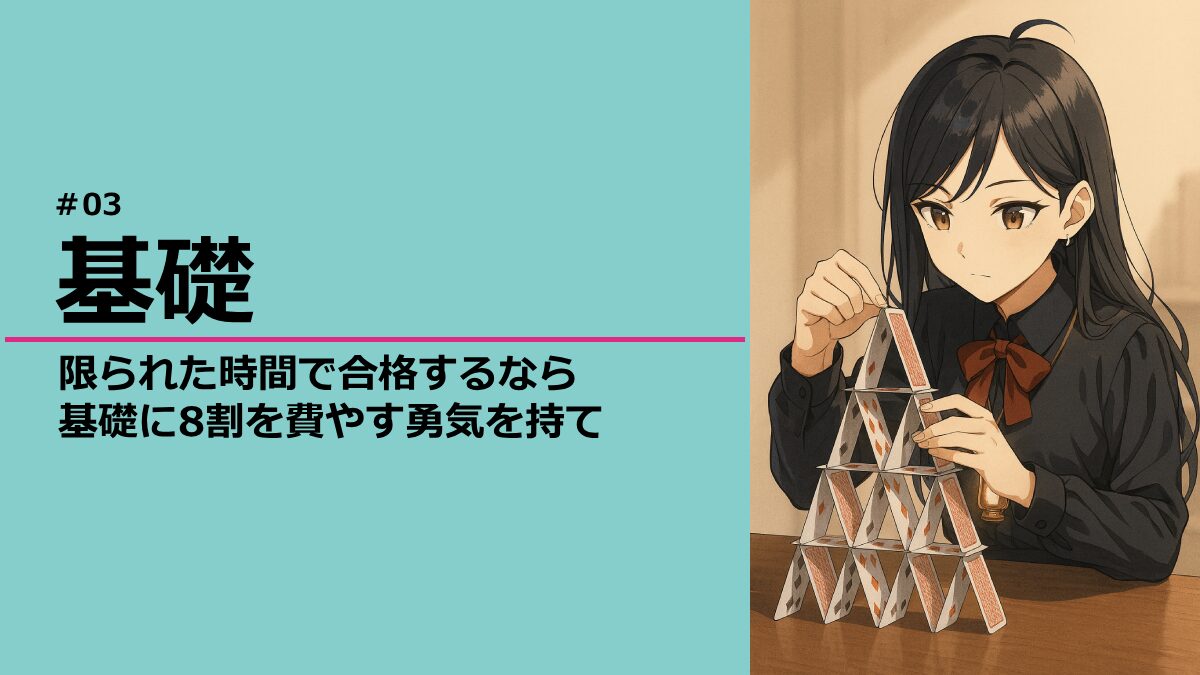
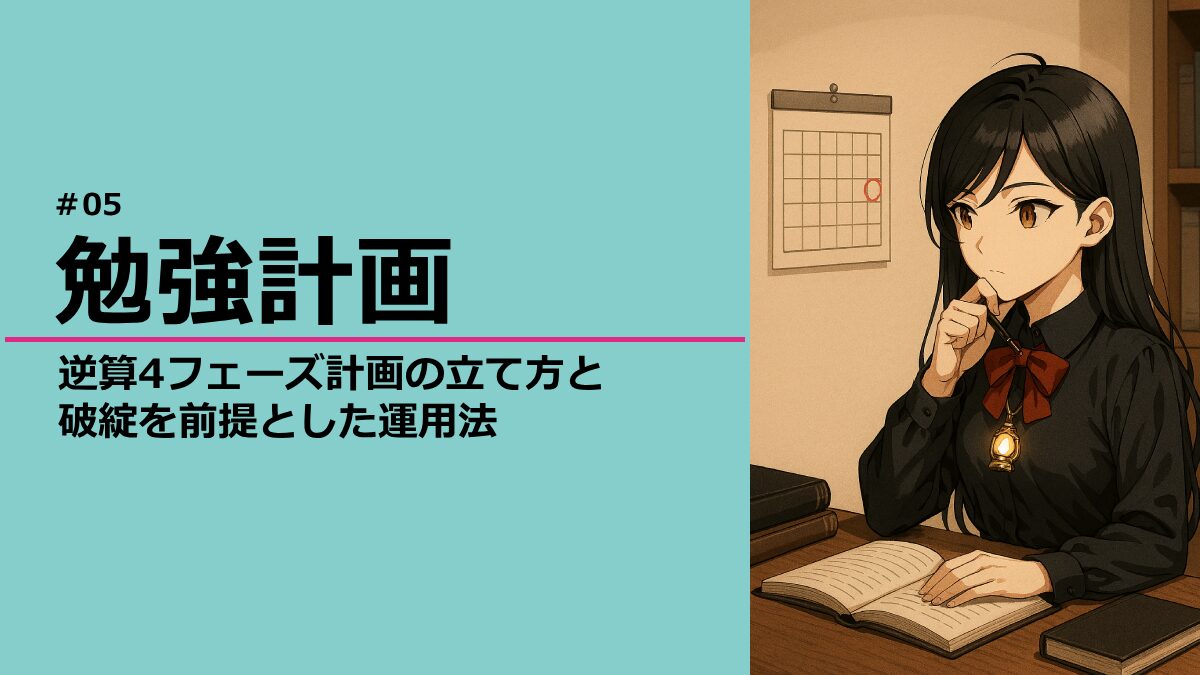
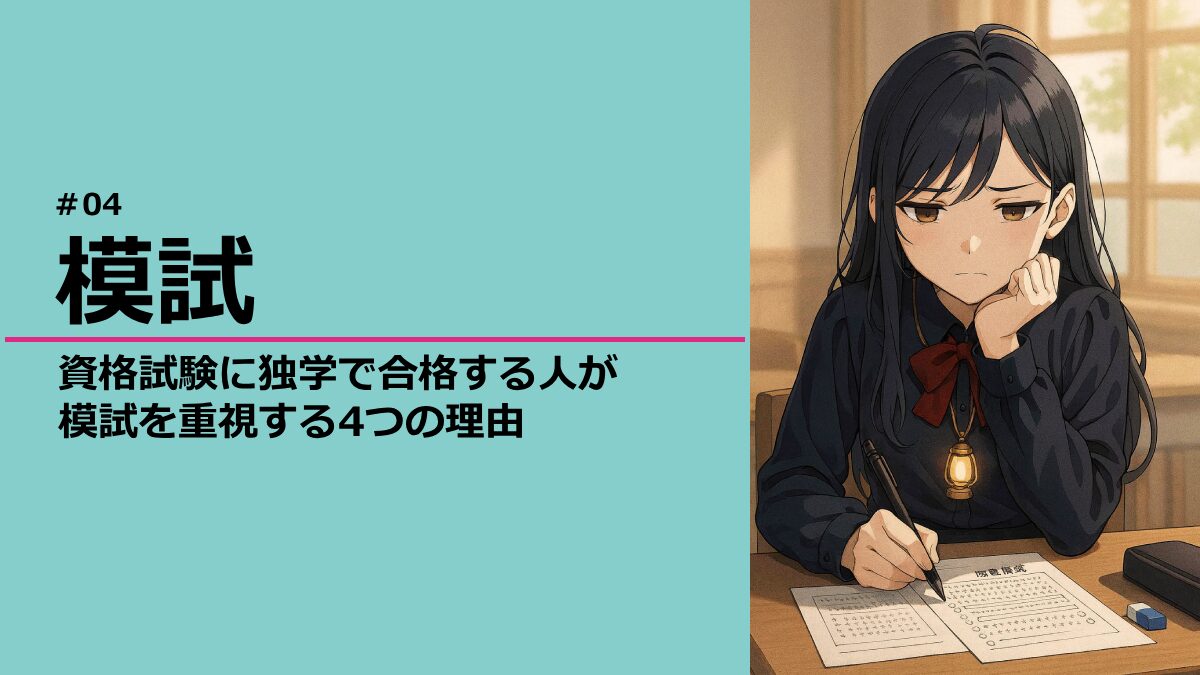

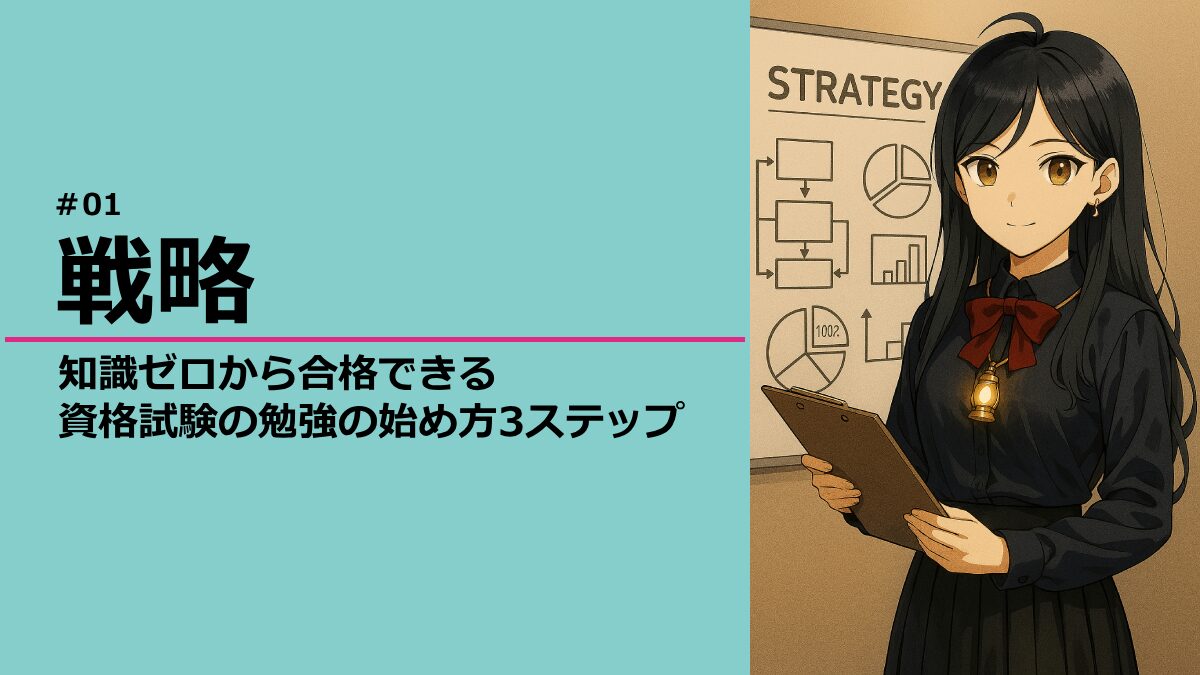
コメント