 灯
灯やる気が出ない、めんどくさい、できることならさぼりたい…
長い試験勉強の中で、こうした感情が生まれるのは当たり前のことです。
しかし、結果を出す受験生というのは、そうした感情に振り回されることなく、「仕組み」によって行動を継続していきます。
勉強を続ける人は、特別に意志が強いわけではありません。
続けられる仕組みを持っているのです。
習慣化の3原則のひとつ「小さく始める」は、意志の力に頼らず、自然に勉強を始めるための鍵。
本記事では、この原則をもとに、勉強のやる気スイッチをONにする仕組みを考察していきます。
「明日から本気出す」が口癖になっている人は、ぜひ参考にしてみてください。


- 大学受験の指導経験は10年以上
- 自身も行政書士試験に独学で合格
- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中
チャンクダウン:目標を細分化して心理的壁を破壊する



勉強しなきゃいけないことが多すぎて、やる気が出ないんです…
受験勉強には、やらなければならないことが山ほどあります。
その膨大な量を前にすると、やる気が削がれ、心が折れてしまうのも無理はありません。
しかし、どんなに大きな目標も、それを構成するのは小さな部分の積み重ねです。
「憲法を覚える」「英語長文を読めるようになる」
そんな大きな目標も、実際は1ページ、1行、1語からできています。
まずは、目の前の課題を小さな単位に刻んでみましょう。
困難は分割することで「始められるサイズ」に変わります。
勉強の目標を細分化して、小さな単位にする。
それは、心理的ハードルを下げるだけでなく、脳の「やる気スイッチ」を押すための準備でもあります。
人間の脳は、作業を始めることで少しずつ興奮状態に入り、やる気が後からついてくる性質があります。
この現象は「作業興奮」と呼ばれ、心理学者クレペリンによって提唱されました。
つまり、「やる気が出たら始める」のではなく、「始めたらやる気が出る」のです。
だからこそ、目標を小さく刻み、「とりあえず1問だけ」「まずは3分だけ」といった行動が、やる気を引き出す最短ルートになります。
チャンクダウンは、作業興奮を引き出すための「着火剤」なのです。
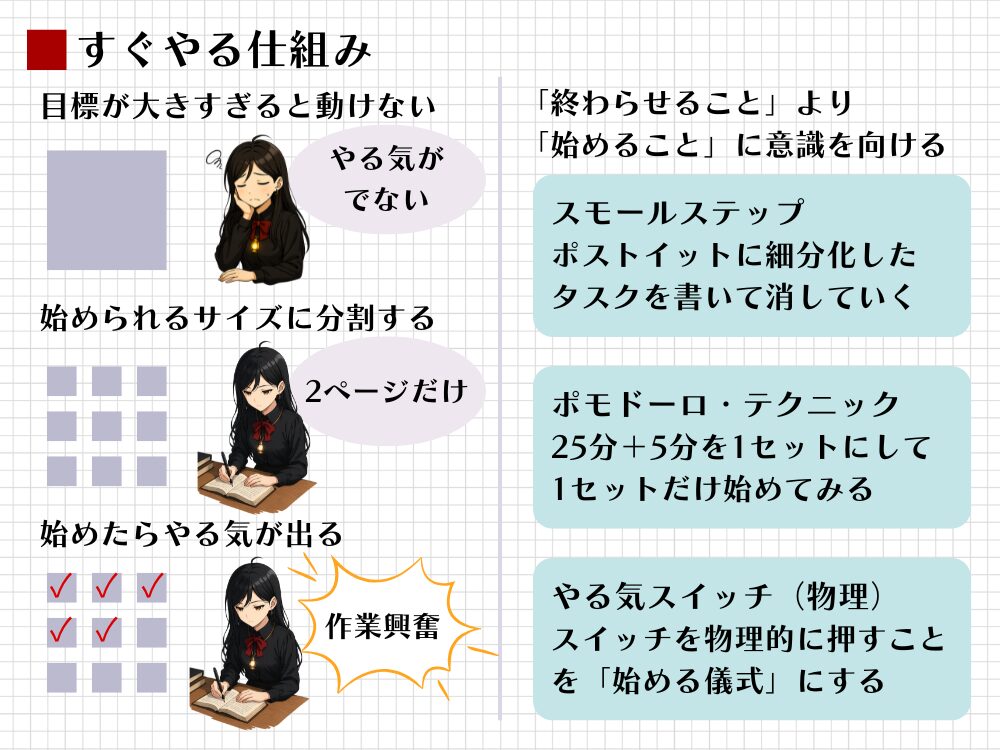
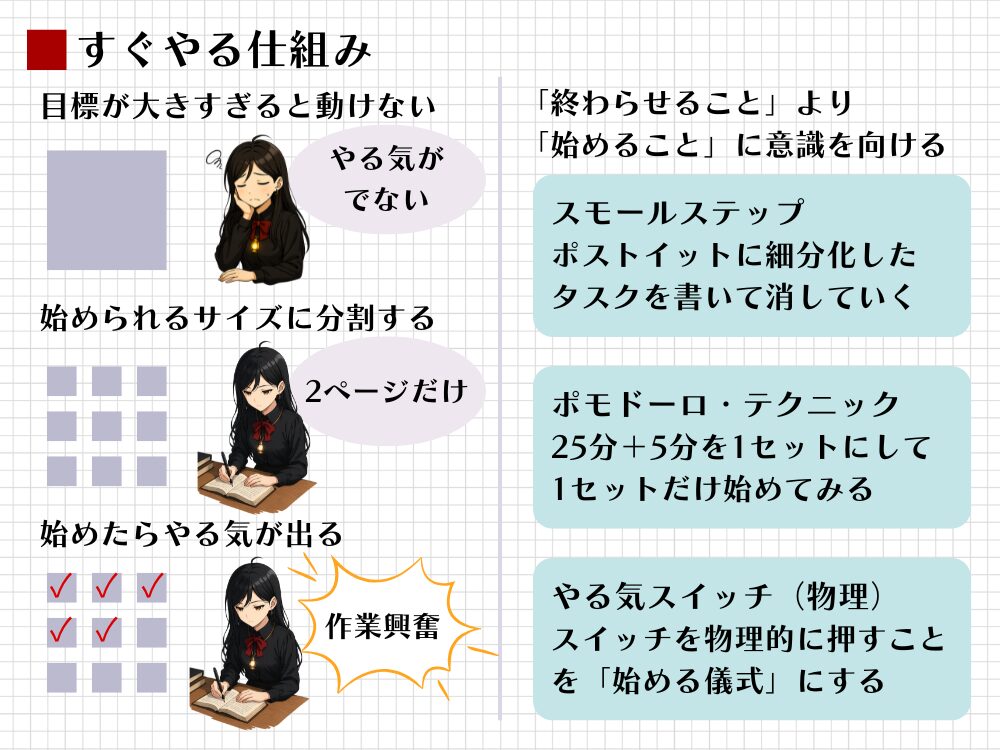
スモールステップ:とりあえず1問からスタートする仕組み



具体的にはどうしたらいいんですか?
こうしたチャンクダウンを仕組化したのが、勉強の「スモールステップ・エンジン」です。
朝、その日の勉強目標を細かいタスクに分けて、大型のポストイットにチェックリストを作ります。
「今日は7科目」「今日は100ページ」「今日は150問」といった膨大なノルマを、「1科目」「10ページ」「10問」といった始められるサイズに細分化しましょう。
始めてしまえば、作業興奮を呼び込み、次の行動につながります。
タスクをクリアするたびに消していけば、達成感とともに勉強が進みます。
そして、その日のチェックリストを手帳に貼っておけば、継続意欲を高める「勉強記録」になります。
勉強を仕組みにして習慣にする。
それは、こうした小さな工夫の積み重ねなのです。
ポモドーロ・テクニック:勉強時間も細分化して集中力アップ



2時間とか言われると、もうその時点でやる気がなくなります…
時間もまた、チャンクダウンの対象になります。
勉強時間そのものを小さく刻むことで、心理的な負担を減らし、行動のハードルを下げることができるのです。
そこで活用したいのが「ポモドーロ・テクニック」。
これは、イタリアの起業家フランチェスコ・シリロが提唱した時間管理術です。
ポモドーロとはイタリア語でトマトのこと。
彼がトマト型のキッチンタイマーを使ってタイムマネジメントをしていたことから、そう名付けられました。
実践方法はシンプルで、25分の作業時間と5分の短い休憩を1セットとして交互に繰り返し、4セット終えたところで15~30分の長い休憩をとります。
こうすることで、高い集中力を長時間維持でき、生産性が向上するとされています。
このポモドーロ・テクニックが優れているのは、「やりたくないことは小さく始める」という基本に適っているからです。
2時間勉強しようと思えば憂鬱でも、「25分+5分」を4セットと考えれば、心理的ハードルはぐっと下がります。
どうしても気乗りしないなら、「今日は最初の1セットだけ我慢してやってみよう」と、小さく始めることができます。
実際にやってみると、25分というのは意外にあっさり終わります。
最初の1セットだけで終わっても、何もしないよりは達成感があります。
そして、始めてみたら調子が出てきて、思っていたより続けられることもよくあります。
もちろんこれは作業興奮のおかげです。
やる気スイッチ(物理):意志に頼らない始める儀式を決めておく



他にも何か始めるヒントってありますか?
勉強を習慣にするには「始める儀式(ルーティーン)」を持つことも効果的です。
毎日同じ動作や同じ手順で勉強を始めることで、脳に「これから集中する時間だ」と知らせることができます。
やる気スイッチ(物理)
- タイマーのボタンを押す
- デスクライトのスイッチを入れる
- PCの電源をOFFにする
こうした物理的なスイッチを押す行為をルーティーンにすると、手を動かすだけで脳が「これから始める」と認識し、自然と集中モードに入っていきます。
そもそもポモドーロ・テクニックも、トマト型のキッチンタイマーという「物理スイッチ」から生まれた工夫です。
小さな動作でも、やる気の着火剤になるのです。
こうした小さな動作を「勉強を始める儀式」として固定しておけば、やる気がなくても自然と勉強モードに入れるようになっていきます。
すぐやる仕組み:終わらせることより始めることを優先する



とにかく少しでいいから始めることが大切なんですね!
ある心理学の実験では、子どもたちを2つのグループに分け、Aには「この課題を全部終わらせよう」と指示し、Bには「この課題を少しずつやってみよう」と伝えたところ、Bの方がAよりも20%多く期限内に課題をやり遂げたそうです。
この実験が示しているのは、「終わらせること」よりも「始めること」に意識を向けた方が、行動につながりやすいということ。
「始めは全体の半分である」と、古代ギリシャの哲学者プラトンも言っています。
やる気が出ないときこそ、始めるための小さな行動に意識を向けてみましょう。
Akari NOTE:すぐやる仕組みまとめ



ここまで読んでくださってありがとうございます。
「すぐやる仕組み」について、少しずつ見えてきましたね。
最後に、この記事のポイントをまとめておきます。
自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!
- 意志ではなく「仕組み」で勉強を続けることができる。
- 目標や時間を小さく刻むことで、始めるハードルが下がる。
- 「始めればやる気が出る」という脳の性質を活かすのがコツ。
- 物理スイッチやルーティーンを使えば、自然と集中モードに入れる。
5分でできる行動:5分間だけ手元の問題集を解いてみる。



勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。




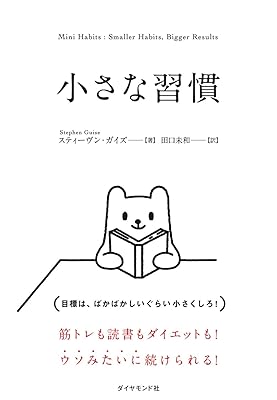
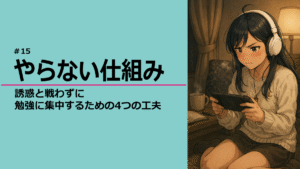



コメント